最近のGoogle検索では、AIが検索結果の要点を自動で要約して表示する「AIによる概要」機能が注目されています。便利な反面、「誤解を招く」「元ページが読まれにくい」と感じている人も増えています。この記事では、そんなAI要約を無効にしたい人のために「オフにする方法」や「設定の注意点」、その背景についてまとめてました。
google検索AIによる概要のオフとは?
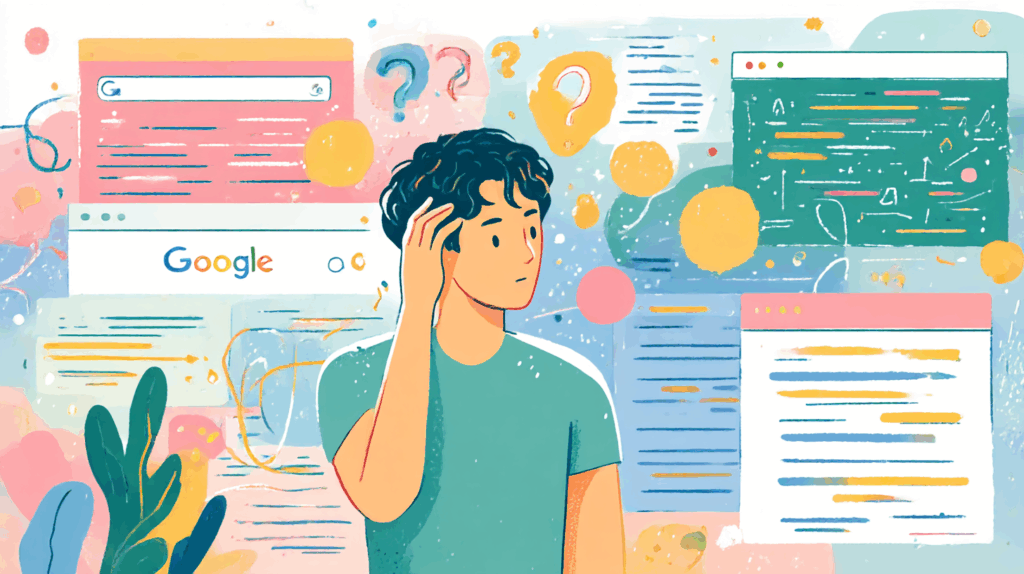
- AIによる概要表示とはどういう機能?
- SGE(Search Generative Experience)の仕組みは?
- なぜ検索結果にAIの要約が出るの?
- 検索体験が変わるメリットとデメリットは?
- 従来の検索とどう違うの?
AIによる概要表示とはどういう機能?
AIによる概要表示とは、Google検索でキーワードを入力した際に、ページを開かなくても内容をざっくり把握できるように「要点だけ」をAIが自動生成して表示する機能です。
具体的には、検索結果の上部に短いまとめ文が表示され、「これを見れば大まかな内容がわかる」という形で情報を提示します。
最近では「SGE(Search Generative Experience)」という名称で実験的に提供されています。
SGE(Search Generative Experience)の仕組みは?
SGEはGoogleが開発した「生成AI」を使った検索体験で、ユーザーの検索意図をAIが理解し、最適な回答を要約形式で提供する機能です。
大規模言語モデル(LLM)が使われており、従来の検索ではリンクの羅列だった部分に「文章での答え」をAIが提示します。
検索キーワードだけでなく、文脈や過去の検索履歴なども解析しながら、カスタマイズされた情報を表示できるのが特徴です。
なぜ検索結果にAIの要約が出るの?
Googleがこの機能を導入した理由は、ユーザーが「できるだけ早く正確な情報にアクセスしたい」というニーズに応えるためです。
長い記事や複数のページを読み比べる手間を減らし、1つのまとめで答えに近づけることで「検索の効率化」を図っています。
とくにモバイル環境では、スクロールやタップ数を減らせることがメリットとされています。
検索体験が変わるメリットとデメリットは?
メリット
- ページを開かずに情報の要点を把握できる
- 検索スピードが向上する
- 複数ページを比較しなくても答えに近づける
デメリット
- 要約が不正確な場合がある
- 元のページが読まれずアクセス減になる可能性
- 情報の出典が明確でないこともある
便利である一方、情報の正確性や引用元の透明性について課題も残されています。
従来の検索とどう違うの?
従来のGoogle検索では、検索結果は「関連性の高いWebページのリンク一覧」が表示され、ユーザーが自分でページを開いて情報を確認する必要がありました。
一方、AIによる要約機能(SGE)は、検索結果の上部にAIが文章で“まとめた答え”を提示してくれるため、リンクをたどらずとも一定の知識が得られます。
ただし、この「答え」はAIによる生成のため、必ずしも正しいとは限らないという点が大きな違いです。
google検索AIによる概要のオフのやり方
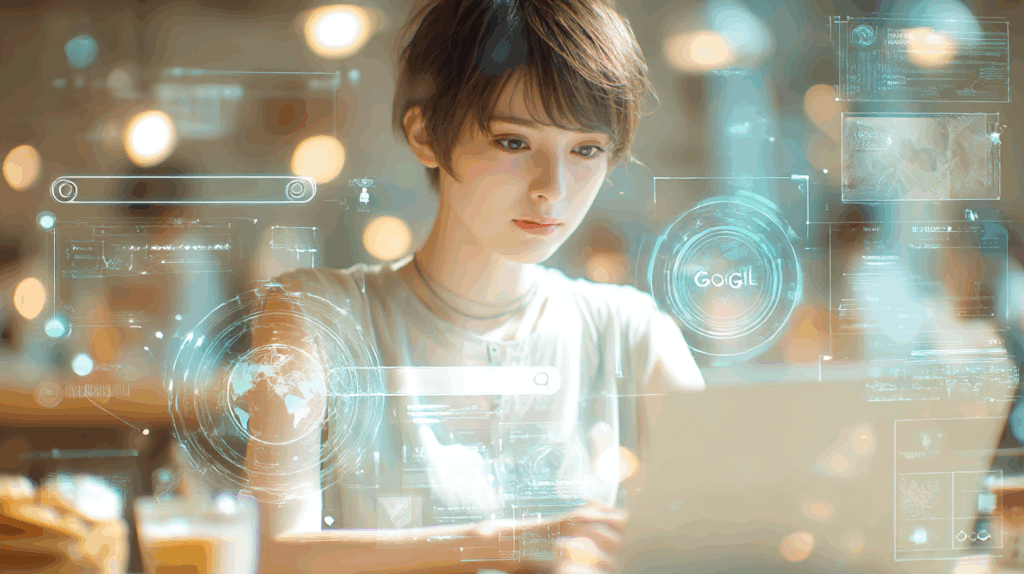
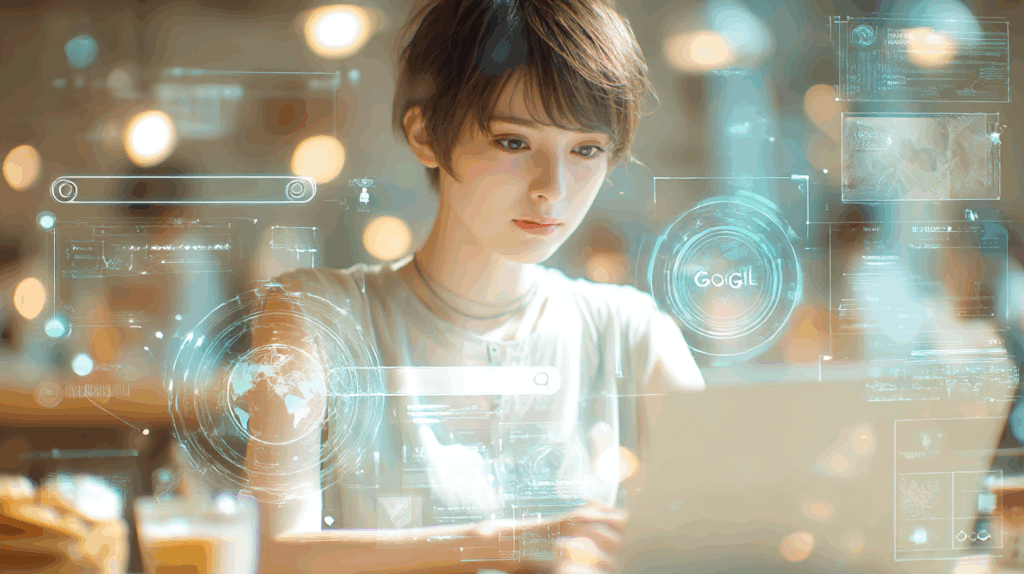
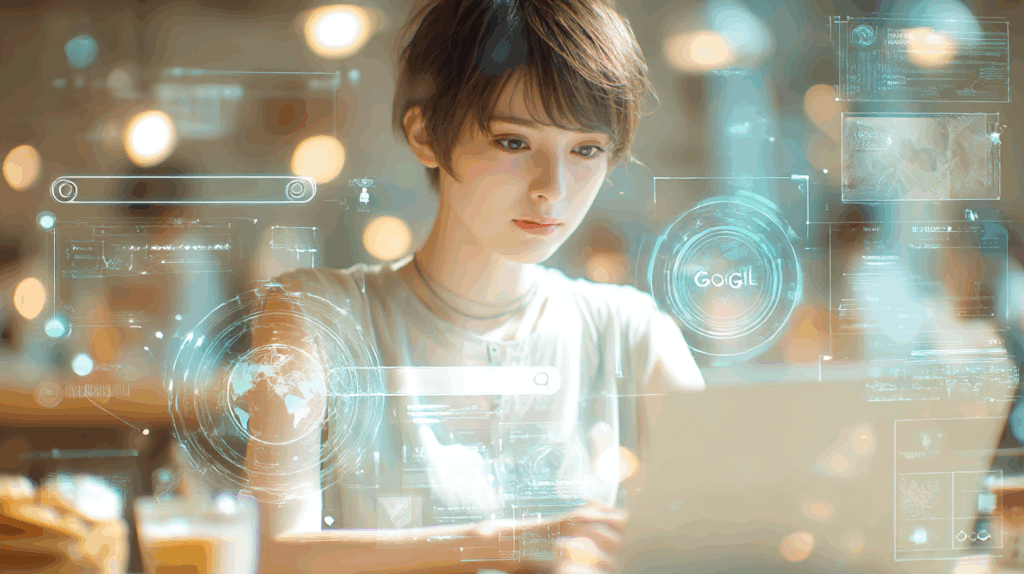
- AI概要を無効にするにはどう設定する?
- GoogleのSearch Labsはどこから変更できる?
- スマホでもAIの概要をオフにできる?
- Chrome拡張機能でAI概要を非表示にする方法は?
- 一時的にAI要約を隠す方法はある?
- Googleアカウント設定での制御方法は?
- 検索履歴やパーソナライズをオフにしたらどうなる?
AI概要を無効にするにはどう設定する?
AIによる概要表示(SGE)をオフにするには、Googleが提供している「Search Labs」の設定から変更が必要です。
現在は試験運用中の機能のため、デフォルトでONになっている場合があります。
設定を無効にすることで、AIが生成した要約ではなく、従来通りの検索結果に戻すことができます。
GoogleのSearch Labsはどこから変更できる?
Search Labsは、Google Chromeブラウザの検索ページ右上にある「実験アイコン(フラスコ型)」からアクセスできます。
そこをクリックすると、SGE(Search Generative Experience)のON/OFFスイッチが表示されますので、トグルをオフに切り替えるだけでOKです。
この機能はGoogleアカウント単位で反映されるため、一度設定すれば同じアカウントでは継続して適用されます。
スマホでもAIの概要をオフにできる?
はい、スマホ版のGoogleアプリやモバイルブラウザからもSearch Labsの設定は変更可能です。
Googleアプリの場合は、右上のプロフィールアイコン →「Search Labs」→「SGEを無効化」で設定できます。
モバイルでもPCと同様に、アカウント単位で反映されます。
Chrome拡張機能でAI概要を非表示にする方法は?
一部のユーザーは、Googleが生成するAI概要をブラウザ側で非表示にしたい場合、Chrome拡張機能を使う方法があります。
たとえば「uBlock Origin」などのカスタムフィルターを使って、特定の要素(SGEのボックス)を非表示にできます。
また、GitHubなどで公開されている「SGE Blocker」などの専用拡張も今後登場が期待されています。
一時的にAI要約を隠す方法はある?
SGEが表示された場合、そのボックス右上に「×(閉じる)」ボタンがあることが多く、それをクリックすればその場では非表示にできます。
ただしこれはあくまで“その検索の一時的な非表示”にすぎないため、次の検索では再びAI要約が表示されます。
根本的に無効にするには、Search Labsからの設定変更が必要です。
Googleアカウント設定での制御方法は?
Googleアカウントの「アクティビティ管理」設定から、検索履歴の保存やパーソナライズをオフにすることで、SGEの精度や表示内容に影響を与えることができます。
設定手順:
- Googleアカウントにログイン
- アカウント設定 →「データとプライバシー」
- 「ウェブとアプリのアクティビティ」→ オフに切り替え
この設定によって、SGEの表示が完全になくなるわけではありませんが、AIが個人の履歴に基づいて情報を調整する精度が下がるため、非表示に近い挙動になります。
検索履歴やパーソナライズをオフにしたらどうなる?
検索履歴やパーソナライズをオフにすると、Googleがユーザーに合わせて調整していた検索結果やAI要約の精度が低下します。
具体的には、過去の検索傾向を反映した補足情報や文脈の自動解釈が少なくなり、より“一般的な答え”に近づく可能性があります。
これにより、AIによる過度な要約や自動生成結果を抑えることができるケースもあります。
google検索AIによる概要のオフが必要な理由



- 誤った情報が表示されることはある?
- 元ページが読まれずに困るケースとは?
- SEOやWeb運営者への影響は?
- ニュースや医療情報では危険性が高まる?
- 「AIで要約された情報」が信頼できない理由は?
- 情報の裏取りが難しくなるのはなぜ?
誤った情報が表示されることはある?
はい、AIによる概要表示には誤情報や誤解を招く内容が含まれる可能性があります。
GoogleのSGE(Search Generative Experience)は大量の情報をもとに要約を作成しますが、元となる情報の信頼性が低い場合や、文脈を誤って解釈した場合に誤った結論を提示するリスクがあります。
特に複雑な専門分野では、微妙な違いが大きな誤解につながることもあるため注意が必要です。
元ページが読まれずに困るケースとは?
AIによる要約が目立つ位置に表示されると、ユーザーが元のWebページにアクセスしなくなることが多くなります。
これにより、本来の情報発信者が提供した詳細情報や、背景の解説が読まれないまま、断片的な情報だけが拡散されてしまうリスクがあります。
特にSEOや収益を目的としたメディアでは、PV(ページビュー)の大幅減少が問題になることもあります。
SEOやWeb運営者への影響は?
SGEが導入されると、検索結果からのクリック率(CTR)が下がる傾向があります。
ユーザーがAIの要約だけで満足してしまうため、個々のWebサイトへの流入が減少し、SEO対策の効果が薄れることになります。
これにより、コンテンツ制作に時間とコストをかけたWeb運営者にとっては、大きな打撃となる可能性があります。
ニュースや医療情報では危険性が高まる?
特に注意すべき分野が「ニュース」「医療」「法律」などの専門性と正確性が求められる情報です。
AIがこれらの情報を要約する際に、文脈を誤解したり、最新情報を見落とすことで危険な誤報になるリスクがあります。
例えば医療情報では、誤ったアドバイスが健康被害や誤診誘導につながる恐れがあるため、必ず元の情報にアクセスすることが推奨されます。
「AIで要約された情報」が信頼できない理由は?
AIは情報を自動で収集・要約するため、情報源の信頼性を十分に評価できないことがあります。
また、要約の過程で主観的な言い回しや、重要な前提の省略が起きると、誤解につながりやすくなります。
「一見わかりやすく見えるが、実は間違っている」というケースがあるため、AI要約を鵜呑みにしない姿勢が重要です。
情報の裏取りが難しくなるのはなぜ?
AIが提示する要約には、参照元のURLや出典が明示されない場合があります。
そのため、ユーザーが「この情報はどこから来たのか?」を確認するのが難しくなり、裏付けを自分で調べる手間が増えてしまうのです。
また、元情報が複数のサイトからの“ミックス”になっていることも多く、検証が困難になる構造的な問題もあります。
よくある質問(Q&A)
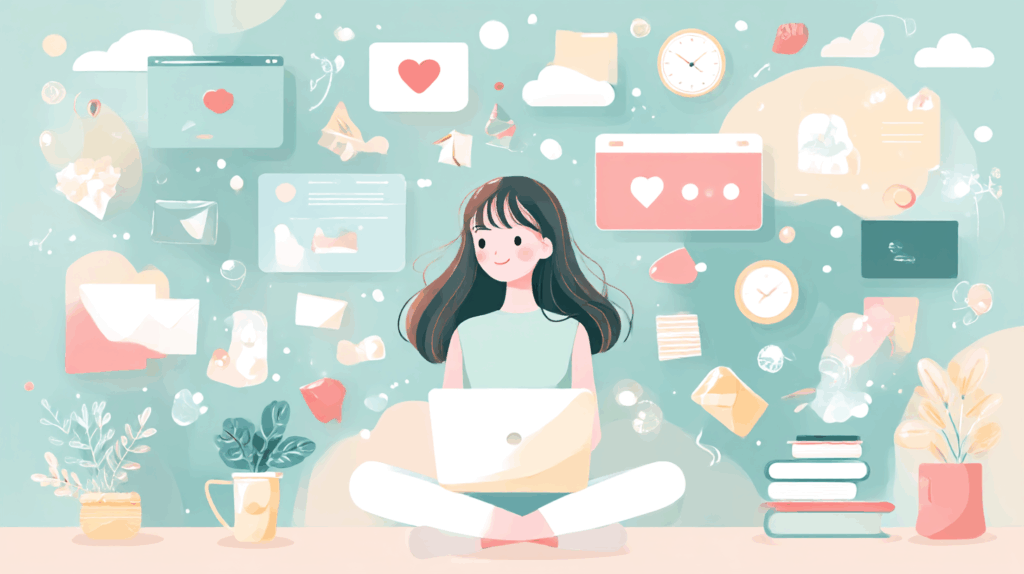
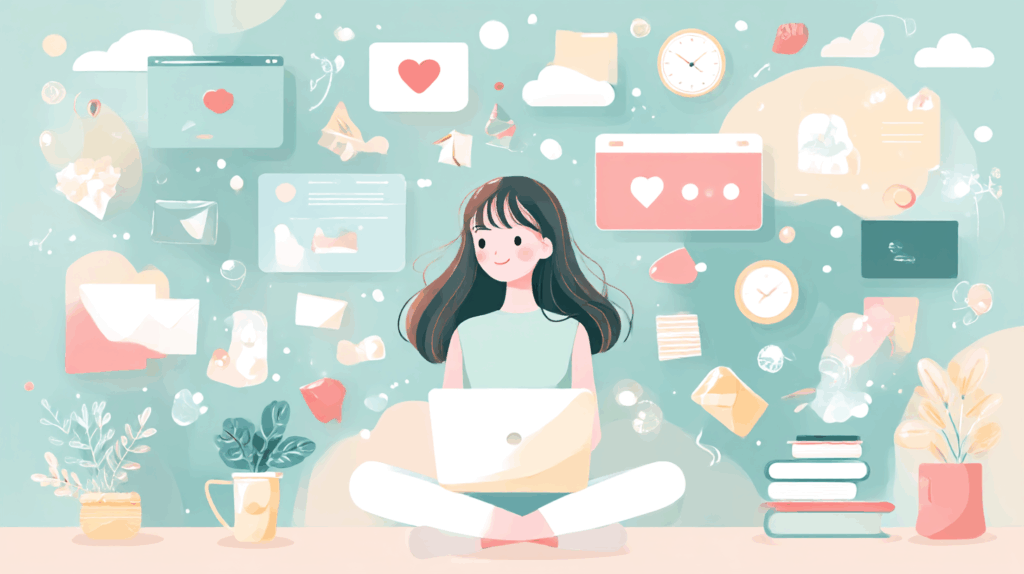
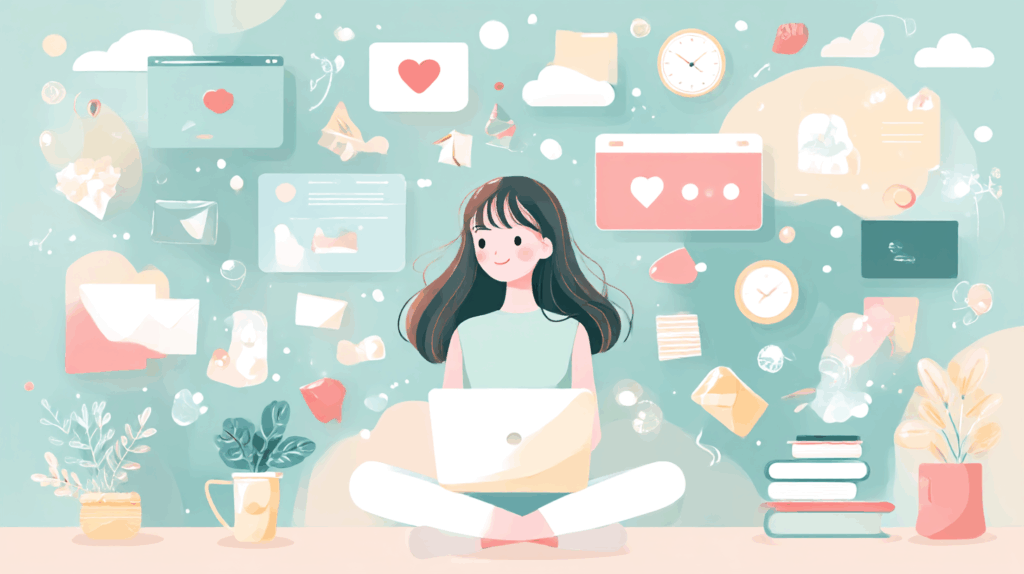
まとめ|google検索AIによる概要オフのやり方と注意点
- google検索AIによる要約は現在テスト中
- ユーザーによっては自動表示されている
- Search Labsからオフにすることが可能
- スマホでは設定場所が異なるので注意
- Chrome拡張での回避方法もある
- 誤情報や省略で混乱するケースがある
- 検索結果から元ページが読まれにくくなる
- SEO影響を気にする人は無効化がおすすめ
- 情報の裏取りには従来検索が有効
- 特に医療・法律系ジャンルは要注意
- 今後もユーザー側で制御できる設計が重要






