OpenAI API を使ってみたいけれど、「料金はいくらかかるんだろう?」と不安に感じていませんか?
本記事では、GPT‑4・GPT‑3.5などのモデル別料金を、わかりやすく日本円で解説します。
さらに、料金を抑える使い方のコツや無料枠の有無、開発現場での実際の費用例まで詳しくお伝えします。
初めてAPIを触る方でも安心して読める内容にしていますので、ぜひご参考になさってください。
- モデル別に料金を整理&日本円目安を紹介
- トークン課金の仕組みと実際のコスト例
- 無料枠や節約テクニックを活用する方法
- 請求タイミングや商用利用の注意点も網羅
openai apiの料金目安は?モデル別にわかりやすく紹介

- APIの料金はどのくらいから使える?
- GPT-4とGPT-3.5の料金差は?
- WhisperやEmbeddingはどれくらい?
- 日本円でどのくらいかかる?為替は?
- トークン課金ってどういう仕組み?
APIの料金はどのくらいから使える?
結論:
OpenAI APIは従量課金制なので、数十円〜数百円程度から利用できます。
理由:
使ったトークン数に応じて課金される仕組みなので、少量のテストや開発なら非常に安価に使えます。
具体例:
たとえば、GPT-3.5(gpt-3.5-turbo)なら1,000トークンあたり約0.0015ドル(約0.25円)。
短めの文章なら、1回あたり0.1〜0.5円未満のことも珍しくありません。
まとめ:
最初から大きな費用はかからず、気軽に試せるのがOpenAI APIの魅力です。
GPT-4とGPT-3.5の料金差は?
結論:
GPT-4はGPT-3.5の10倍以上の料金がかかります。
理由:
モデルの処理能力や性能が大きく異なるため、それに応じて価格設定も大きく違います。
料金比較(2024年時点)※1,000トークンあたり:
| モデル | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo | $0.0015 | $0.002 |
| GPT-4(8k context) | $0.03 | $0.06 |
| GPT-4 Turbo(128k) | $0.01 | $0.03 |
※GPT-4 Turboはコストを抑えたGPT-4の派生版です。
まとめ:
価格重視ならGPT-3.5、精度重視ならGPT-4と、使い分けがカギになります。
WhisperやEmbeddingはどれくらい?
結論:
Whisper(音声認識)やEmbedding(ベクトル化)も低コストで使えます。
理由:
どちらもGPTモデルとは異なる用途で、比較的リーズナブルな単価が設定されています。
価格目安:
| サービス | 単位 | 価格(USD) |
|---|---|---|
| Whisper | 1分の音声 | 約$0.006 |
| Embedding | 1,000トークン | 約$0.0001〜0.0004 |
まとめ:
テキスト以外の処理にも使える機能が揃っており、用途が明確なら非常にコスパが高いです。
日本円でどのくらいかかる?為替は?
結論:
月あたりの利用料は、個人利用なら数百円〜数千円程度が一般的です。
理由:
OpenAI APIは米ドルでの課金ですが、実際の支払いは日本円に換算され、為替レートに応じて変動します。
為替のポイント:
- クレジットカードの請求時に為替換算(例:$1 = 150円)
- API料金表の単価 × トークン数 → 米ドル合計 → 日本円で支払い
- 高額利用でない限り、数百円〜3,000円程度が目安
まとめ:
使用頻度が少なければ、月1,000円以下に収まることも多く、コストを気にせず始められます。
トークン課金ってどういう仕組み?
結論:
OpenAIのAPIは、入力テキスト+出力テキストの合計トークン数に基づいて課金されます。
理由:
1トークンは英単語の一部や1〜数文字を指し、文の長さによって消費量が変わります。
トークンの目安:
- 1,000トークン ≒ 英文750語程度、または日本語で約500〜700文字相当
- 質問文と回答文の両方が課金対象
計算例(GPT-3.5 Turbo):
- 入力:300トークン(質問)
- 出力:500トークン(回答)
- 合計:800トークン → 約$0.0012(= 約0.2円)
まとめ:
トークン数を意識すれば、精度とコストのバランスを取りながら効率よくAPIを使えます。
openai apiの料金を安く抑えるには?使い方のコツ
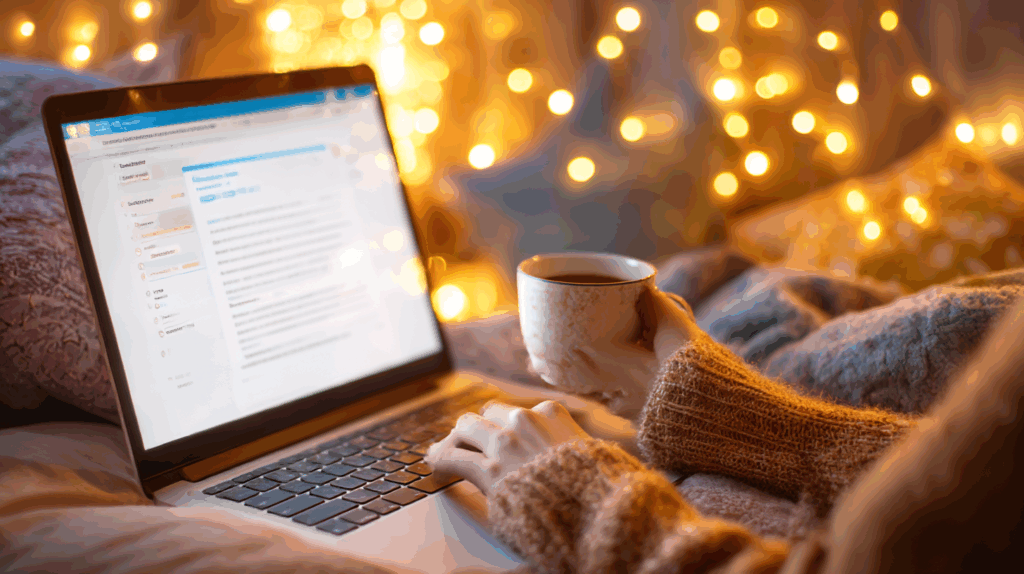
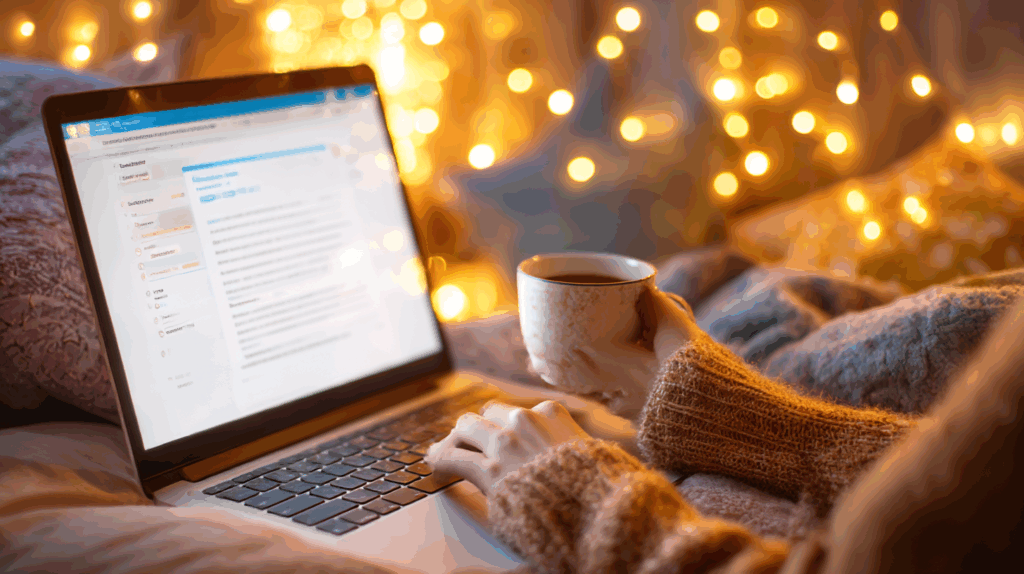
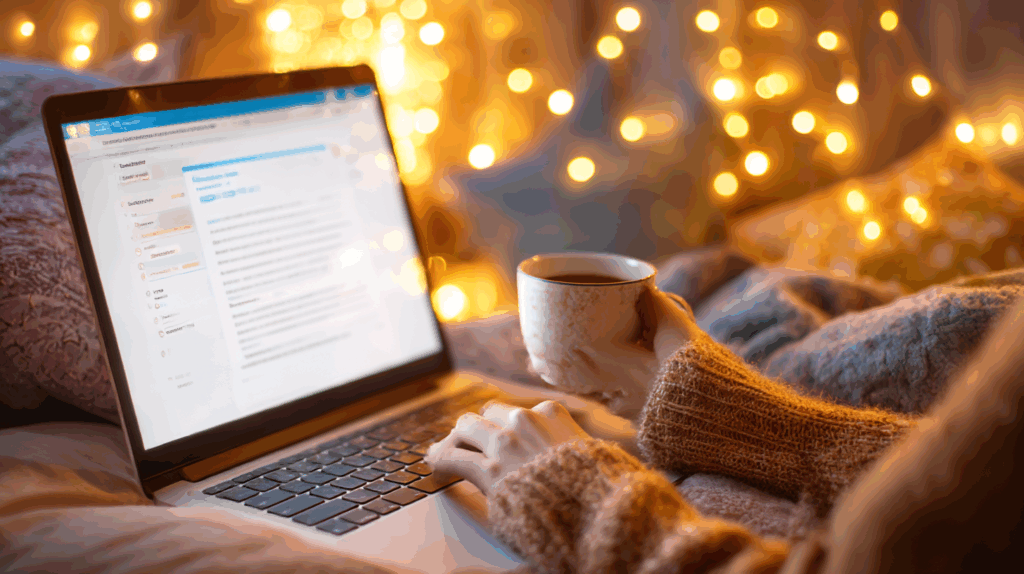
- 無料枠やトライアルはある?
- GPT-3.5とGPT-4、どっちがお得?
- トークン消費を抑えるプロンプトの書き方は?
- 不要なAPIコールを減らすには?
- 利用上限の設定方法は?
無料枠やトライアルはある?
はい、OpenAIには新規アカウント向けに無料クレジットの提供があります。登録時に一定額(たとえば$5分など)が自動で付与され、これを使って各種APIを試すことができます。
クレジットの有効期限は通常3カ月程度なので、アカウントを作成したら早めに使うのがベストです。課金登録をしなくても利用できるため、「まずは試したい」という方にとってはとても便利です。
ただし、無料クレジットではGPT-4や高負荷なモデルは制限されていることがあるため、試す内容に応じて注意が必要です。
GPT-3.5とGPT-4、どっちがお得?
コストパフォーマンスを考えるなら、GPT-3.5の方が断然お得です。GPT-4は高度な理解力や論理構成に優れていますが、その分料金も10倍以上になります。
一方、GPT-3.5は多くの業務や日常的なタスクにおいて十分な性能を発揮します。とくに文章生成やFAQ回答、アイデア出しなど、スピードと低コストを求める用途では3.5が圧倒的に効率的です。
高精度な判断や複雑な推論が必要な場面ではGPT-4が有利ですが、ふだん使いにはGPT-3.5の活用でコストを大きく抑えられます。
トークン消費を抑えるプロンプトの書き方は?
APIの料金はトークン数に比例するため、プロンプトの書き方を見直すだけで大幅にコストを削減できます。
ポイントは「短く・具体的に・無駄を省く」こと。たとえば、同じ指示でも冗長な言い回しや説明を削るだけで、トークン数は大きく変わります。
また、繰り返し使う定型プロンプトはテンプレート化して管理し、必要な情報だけを追加する運用がおすすめです。出力トークン数の上限(max_tokens)を明示するのも効果的です。
無駄なやり取りを避け、1回のリクエストで完結するようにプロンプト設計することが、節約の近道です。
不要なAPIコールを減らすには?
トークンの節約だけでなく、「APIを呼び出す回数」そのものを減らすことも、コストを抑えるうえで重要です。
たとえば、何度もリトライして期待する結果を得ようとするよりも、最初のプロンプトの質を高めるほうが効率的です。また、処理結果が変わらない場合は、キャッシュや履歴を使って再利用する方法も有効です。
開発環境では、デバッグ中に何度も無駄なリクエストを送ってしまいがちなので、検証中はダミーデータを使う、事前に設計を整理するなどの工夫が必要です。
定期処理や自動実行の際にも、スケジュールや条件分岐を設定して、最小限の実行回数にすることがポイントです。
利用上限の設定方法は?
OpenAIでは、月ごとの利用上限を設定することができます。予期せぬ高額請求を避けるためにも、あらかじめ予算に合わせて上限を決めておくのが安心です。
設定はOpenAIの管理ダッシュボードから簡単に行えます。
- OpenAIのダッシュボードにアクセス
- 「Usage Limits」のページを開く
- 月ごとの上限額(USD)を入力して保存
個人利用では1,000円程度に設定しておけば、試しながら安心して使うことができます。
業務用途の場合は、実際の使用量に応じて随時見直すのがおすすめです。
openai apiの料金に関するよくある質問まとめ



- 料金の請求タイミングはいつ?
- クレジットカードなしで使える?
- 個人利用と商用利用で価格は変わる?
- 複数ユーザーで使うときの料金は?
- API使用量の確認方法は?
料金の請求タイミングはいつ?
OpenAI APIの料金は毎月末に締めて、翌月に請求が発生します。
たとえば、7月に利用した分は、7月末に合計金額が確定し、8月上旬に請求が行われます。
課金は基本的にクレジットカード払いで、カード会社のタイミングによって実際の引き落とし日は前後します。
「予想より高くなっていた!」ということがないよう、ダッシュボードで月中も使用状況をチェックするのがおすすめです。
クレジットカードなしで使える?
結論として、本格的にAPIを使うにはクレジットカードが必要です。
ただし、OpenAIの新規登録時に提供される無料クレジット($5分など)を使う分には、クレジットカードを登録しなくても利用可能です。
無料クレジットが使い切れると、それ以降のAPI呼び出しには課金情報の入力が求められるため、継続利用する場合はクレカ登録が前提となります。
一部法人では、事前申請によって請求書払い(Invoice対応)を選択できる場合もありますが、基本はカード決済が標準です。
個人利用と商用利用で価格は変わる?
OpenAI APIの料金そのものは、個人利用も商用利用も同じです。
商用で利用する場合も、特別なライセンス契約などは不要で、利用規約の範囲内であれば自由に使えます。
ただし、使用量や体制によっては法人契約(Enterprise Plan)への移行を検討するケースもあります。
たとえば、社内で複数名が使う・大量トラフィックを処理する・SLAやセキュリティ要件が必要、などの場合です。
基本的な料金は誰でも共通なので、スタートは個人契約で問題ありません。
複数ユーザーで使うときの料金は?
複数人でOpenAI APIを使う場合、チーム単位で1つのアカウントを共有するか、Organization(組織)機能を使う方法があります。
組織アカウントを作成すれば、ユーザーごとのAPIキー発行や利用制限の管理が可能になり、誰がどれだけ使っているかを明確に把握できます。
請求は組織単位で合算され、全体の利用量に応じて課金される仕組みです。
ただし、ユーザーごとの「個別課金」ではないので、コントロールするにはロール管理や制限の設定が重要です。
API使用量の確認方法は?
自分がどれくらいAPIを使っているかは、OpenAIのダッシュボードからリアルタイムで確認できます。
確認手順は以下の通りです:
- OpenAI ダッシュボードにログイン
- 「Usage(利用状況)」タブを選択
- 日ごと・モデルごとに使用トークン数や金額を確認可能
また、「Usage Limits」の設定をしておけば、あらかじめ月額上限金額やトークン数に制限を設けることもでき、安心して利用できます。
よくある質問(Q&A)
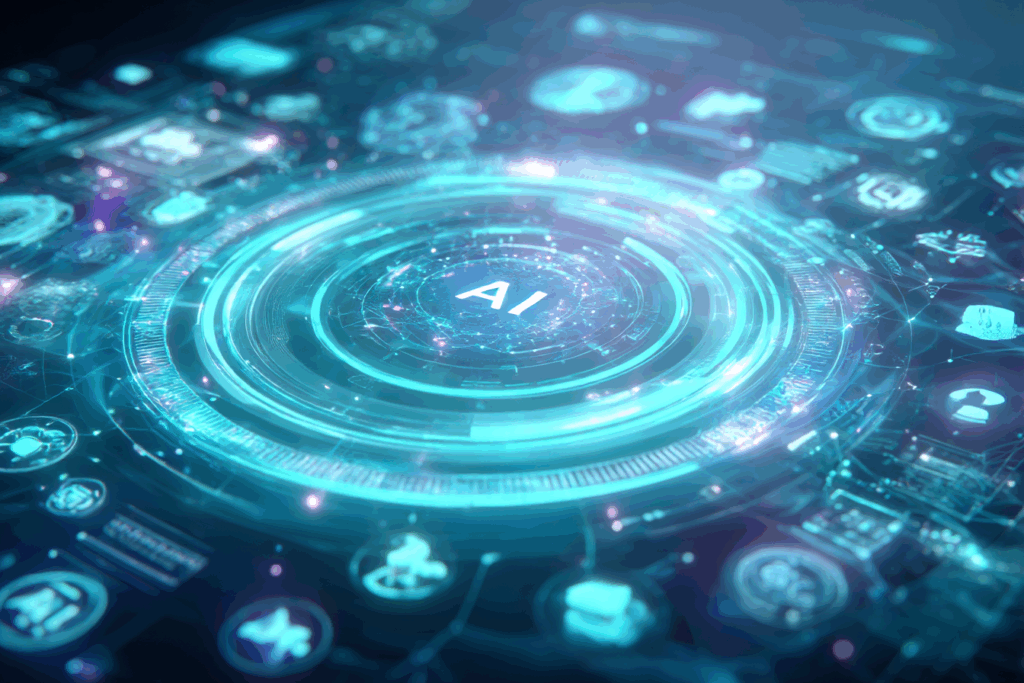
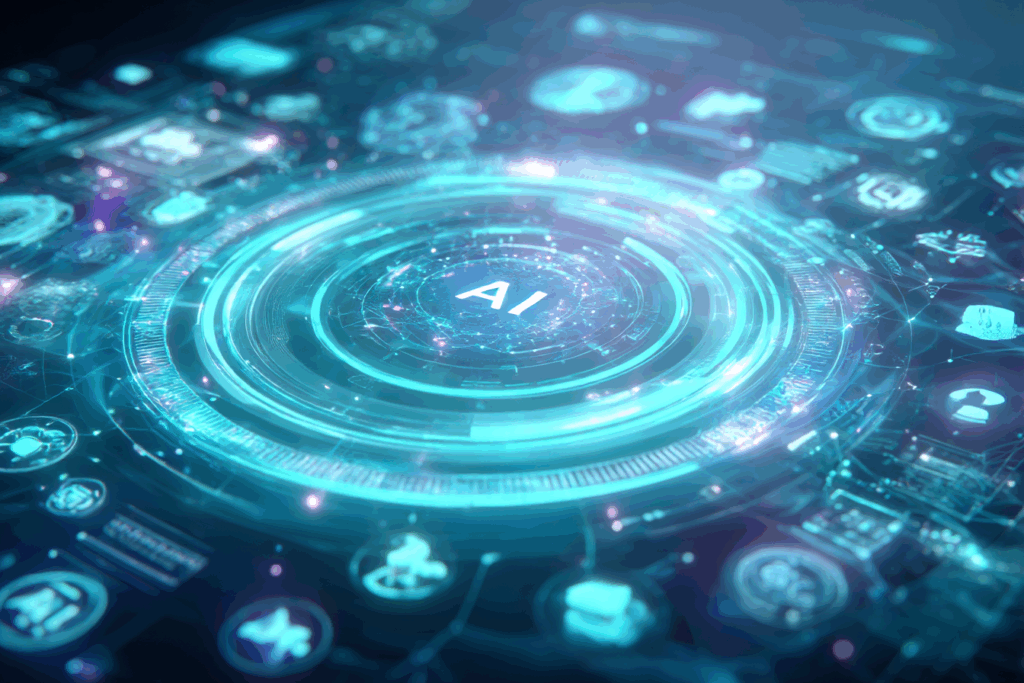
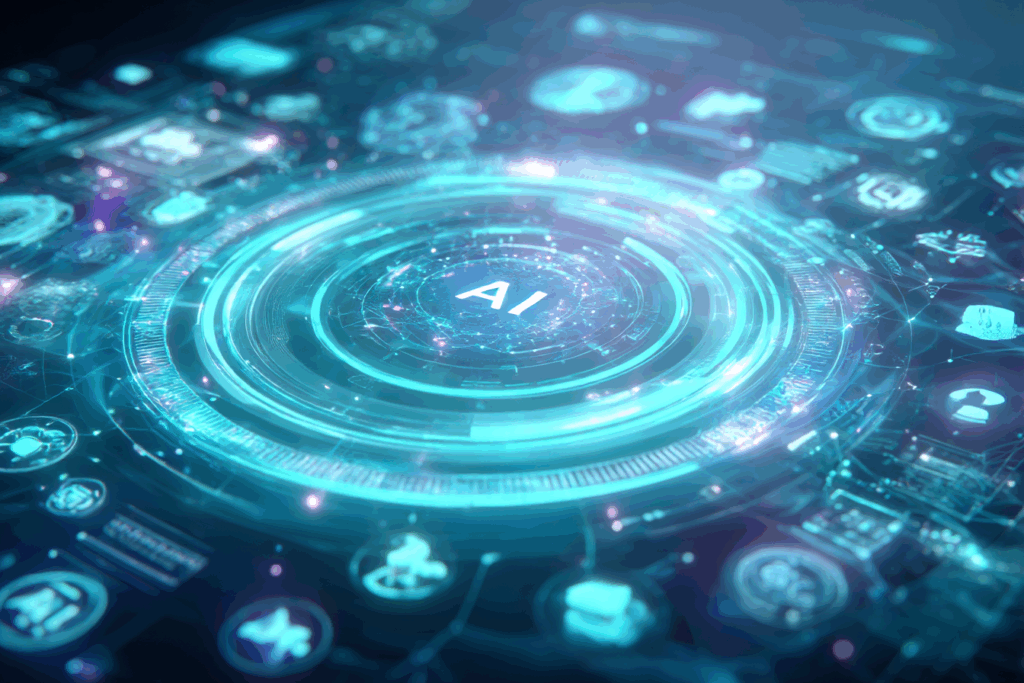
まとめ|OpenAI APIの料金の目安をモデル別にわかりやすく解説
- OpenAI APIは使った分だけ課金される従量制
- モデルごとで価格差が大きく、GPT‑4は高価
- 日本円換算で月数百〜数千円が目安
- 無料クレジットでまずは試せる
- プロンプトの工夫でトークン節約可能
- 呼び出し回数もコストに直結する
- ダッシュボードで利用上限設定ができる
- GPT‑3.5とGPT‑4の使い分けがコスパ最適化のカギ
- 請求は月末締め・翌月支払い
- 商用利用でも課金体系は同じ






